災害にみまわれる自治体の経験に学ぶ〜大分県日田市-視察2日目午前
10月28日(火)午前 日田市
地域防災力向上に向けた取組について
日田市は度重なる自然災害の経験を踏まえ、行政と地域が一体となって災害に強いまちづくりを推進するというもの。
町は、豊かで美しい水があるという天領であり林業で成り立ってきた歴史がある。
天領ということで誰でも入り込めた都市であることで、江戸時代最大の私塾「咸宜園(カイギエン)」ことごとくよろしという意味で、5,000人の門下生がいたとのこと。興味深い歴史を持つ街である。
林業で成り立ってきた町も、豪雨災害では、山腹崩壊も起きている。
1.地域防災計画の策定と修正
50年に一度の大規模災害が、10年に一度、5年に一度、さらには3年に一度となってきている。このことからも、
1、災害対策基本法第42条に基づき地域防災計画を策定しているが、毎年見直しを行っている。
大分県に水害をもたらす大雨のパターンは①南西風パターンと②南東風パターンがあるが、いずれにしても度々やってきている。本当に苦しめられているということを感じた。
2.個別避難計画の推進の取り組みは素晴らしい。
今年度中に、同意された方全員の計画策定を完了するということ。
令和2年の豪雨災害を契機に、個別避難計画の作成を最優先事項として位置づけた。
自治会を単位としたモデル事業から始まり、福祉職・民生委員・自主防災組織等との連携を図りながら、マイ・タイムラインを活用した避難計画の策定と避難訓練を実施しているということだ。

3.自主防災組織の強化と情報伝達体制の整備は、地域ごとの自主防災会を再編し、班単位で自己完結的に機能する体制を構築している。


町内会長さんたち自らが、ポスターに! これはインパクトある。
さらに、学習帳にして、各自治会の小学生へ配布。

学習帳には、タイムラインや、自治会のハザードマップも。

また、防災士の育成や防災訓練への助成、出前懇談会の開催などを市が率先して戦略的に推進している。
防災士も一度なったらそのままではなく、お声をかけて役割を発揮していただいたり、研修を行なったりされているということで、大切な取り組みだと思う。
私も家庭防災員だが、再度の研修なども自分で求めるほかない。せっかくの資格を活かす取り組みは行政が動くことが大事だと思った。
災害時の情報伝達手段として、防災メール、ケーブルテレビ、防災スピーカー。そして災害時はスピーカーの音が聞こえなくなるので、それを流す防災ラジオ(280MHz帯)を希望者に配布している。 私たちが横浜市に求めていることが実践されている。
多重的な手段を整備し、情報の確実な伝達を目指していることがよくわかった
4.被災後の最大の懸案は、罹災証明の発行だ。
ともかく早く発行しようとすると、職員が疲弊する。
そこで、デジタル技術の活用(防災DX)を、令和5年の豪雨災害を受けて、罹災証明書の迅速な発行を目的とした「罹災証明迅速化ソリューション」を導入。AIやGISを活用した住家被害認定調査の効率化により、従来の作業時間を57%削減する成果を上げている。

この取組は「Digi田甲子園2023」において内閣総理大臣賞を受賞しているとのことだ。市民の利益が進むことは素晴らしい。
5.ドローンによる災害対応支援に力を入れているのは、
災害時の孤立地域への支援が、道路の寸断で進まなかった経験から。ドローンによる被災状況の撮影や救援物資の搬送を実施している。行政・消防・警察・企業等との連携により、実践的な訓練を通じて災害対応力の向上を図っており、地域住民を巻き込んだ防災授業や実証実験も行われている。
以上のように、日田市は「災害に強いまちづくり」を目指し、計画の策定・地域との連携・デジタル技術の活用・実践的訓練など多角的な取組を展開している。日田市の水害の歴史を伺うと、踏まれても踏まれても立ち上がるという印象。
しかし、繰り返される災害とその復旧の費用が小さな町には重すぎる現実としてのしかかってきていることを知る。ここは国は力を入れて行くべき分野だ。
近年の九州地方を襲う線条降雨帯のほとんどの影響を受けていたことがわかった。
最後に、職員の方の実感のこもったメッセージ。

ありがとうございました。





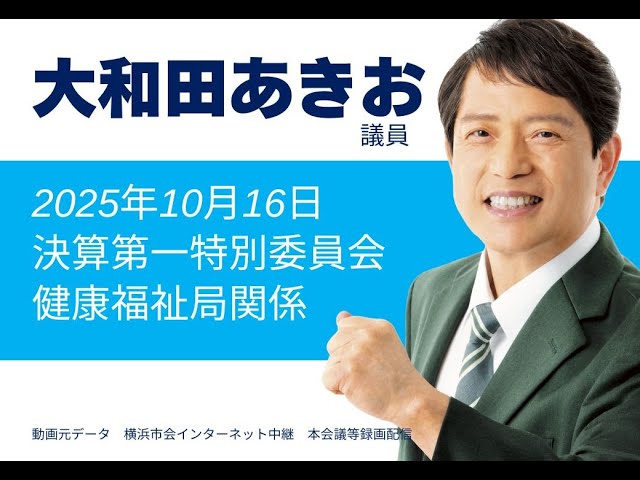 生活保護、介護保険料、国民健康保険料について
生活保護、介護保険料、国民健康保険料について
 横浜国際競技場はネーミングライツをやめて、...
横浜国際競技場はネーミングライツをやめて、...
